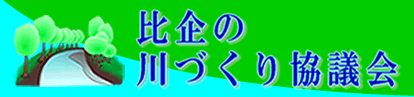 |
 |


3月8日(日)午後より、東松山市松山市民活動センターに於いて、東松山市環境産業部エコタウン推進課主催による市民環境会議が開催されました。3つの目標「将来世代の豊かさを守る持続可能な暮らし」「恵みをもたらす里山、農地、水辺の保全」「市民、地域のチカラが発揮される協働のマチ」のテーマの中の「水辺の保全」の先進的事例の紹介で、朝霞市の「黒目川に親しむ会」の藤井由美子代表からの講演を行って頂きました。
県内でも古くから、河川改修で行政(県土整備事務所)、河川工事・設計会社、市民・住民、専門学者らによる協働事業として「多自然川づくり」を実施してきたことで知られ、その成果はH13年度土木学会でも「土木学会デザイン賞」を授与されるほど素晴らしいものです。
特に、東京都東久留米市、埼玉県新座市、朝霞市の人口密集地(合計人口40万人)にもい拘わらず、水質保全、多様な生き物の回帰、商店街を巻き込んだマチづくり、小・中学生の環境学習の場の創設など、東松山・滑川町・吉見町を貫流する市野川に大いに参考になる講演でした。
■県土整備事務所から、測量業務『H26年度 河川改修工事(モニタリング業務委託)』が発注された
去る2月に東松山県土整備事務所河川砂防部より発注された市野川蛇行河川部の縦横断測量(約1.4Km)は、H21・22年に当協議会が河川整備基金から助成金を受けて実施した「市野川、市民による順応的事業の実施(2WAY方式のモニタリング調査)」を継続し、新川と蛇行河川の保全と有効性を検証する目的になっています。3月2日(月)午後より県土整備事務所・開発測量業者・当協議会(&市野川水系の会)の3者が現地集合して、調査測線(横断測量)の現地確認を実施しました。測量会社は(株)都市開発コンサルタンツ(本社:東松山市)で、当協議会からの参加者は、千葉さん・日下さん・渡辺の3名でした。
行政、測量業者、市民による現場立ち合い⇒
■河川改修の測量とモニタリング測量のちがい
今回の測量延長は約1,350mであり、蛇行河川域(A、B、C、D区間)約850m、直線河川域約500mの縦断測量(20mピッチ)と66測線の横断測量を実施するものです。この測量方法は、国が定める河床変動量調査に準拠して行う調査で、起点(D地区)から終点(A地区)に向かって、20mごとの河床高を求めて縦断図を描くと同時に、その地点の横断図を描くものです。いわゆる、河川計画を行う際の立体現況図の基になるものです。
一方、5年前に私達市民が行った縦横断測量は、河道内微地形を把握する方法で、ハビタットの分布(淵、トロ、早瀬、平瀬の連続分布―Channel Geomorphic Unit―)ごとに縦断・横断図を描くやりかたに従ったものです。従って、均一20mごとの河床変化を捉えたものではありません。測量指導とプログラムの提供は、(独)土木研究所自然共生センターの萱場祐一博士より行われたものであり、この5年前の測線データと今回の測量データをミックスして、河床やハビタットの変化を評価しようとするものです。
蛇行河川(D区域)の測量起点の確認⇒

■2つの測量データをミックスして利用するために
その為に、県土整備事務所斉藤課長、夏目主任、測量士2名と立ち合いの基に、代表的なD区間の釜淵(水深約3.1m)、C区間のドンブリバチ(約1.8m)、新川の分・合流地点、飛び石、又五良水路の出口(A区間)、滑滝(A区間)など、ハビタットの特徴点や地形変換点のモニタリング重点箇所の選点を行い、新たに18測線の追加点を決定してきました。
これまでの市民によるモニタリング測量は、予期せぬ素掘り新川土羽の崩壊(C区間)・土砂流出と堆積(B区間)など大きな地形改変、体力的衰え(班編成不能)や機材の不備などにより、継続出来なかったので、今後、県土整備事務所が継続実施して蛇行河川の保全と上流域の順応的な改修工事を進められることは大変意義深いことと考えております。当協議会としても、「市野川水系の会イン滑川」の皆様と連携して、全面的に協力・支援していく予定です。
3者による打合せ協議(A区域)⇒
以上 写真:千葉、 記録:渡辺


埼玉県主催第21回 『川の再生交流会~きれいな川を次世代へ川の国埼玉~』(埼玉県河川環境団体連絡協議会の協力)がさいたま市民会館うらわで開催されました。栄東中学・高等学校コーラス部の皆さんの歌声で始まり、川にやさしい浄化槽フォーラム埼玉代表の大石さんの報告「排水マナーの向上と排水処理施設の完全達成を目指して」で午前の部は終了。全体参加者は、主催者発表で約650名とのことでした。比企の川づくり協議会からは6名が参加しました。
⇒会場のオープニングコーラス

1月29目(木)朝霞台・朝霞市産業文化センターで、多自然川づくりの普及研修会として、いい川づくり研修会が実施されました。主催は「埼河連」・「NPO全国水環境交流会」で、埼玉県河川砂防課の協力、国土交通省の後援を得て、前年度(2回目)さいたま新都心の国交省関東地整局の会議室で、東京都・埼玉県・千葉県の合同企画で行われたものの続き(3回目)です。
今年は、埼玉県単独開催で、今回は埼玉県単独のいい川づくりがテーマでした。埼玉県の川づくり課題は、県民の圧倒的多数の住民が住む県中・南部の平低地河川にあります。
高度成長以前の昭和30年代から、急激な都市化で住宅が増えて、雨が降れば排水の悪い低地は慢性的に冠水します。そして治水・排水機能優先で、川は深く広大になり、崩落防止の鋼矢板護岸になっており、さらに、都市化に下水インフラが追いつかず、生活排水が河川に流れ込み水質悪化をもたらしています。
また一方で、県北西部の丘陵地では、荒川の治水計画の一環で、平地に広大で高い堤防の川づくりを行っています。数年前より、県では100カ所の川の再生プランや流域のまるごと再生等を行ってきましたが、多くは標準断面で河岸と護岸一体のブロック(れんが)張りの水際や、布団カゴで固めた典型的な定規断面の川づくりが主流でした。県行政内部でも、ようやく多自然川づくりの自主的研究や改修・施工計画も見られ始めましたので、今回の研修会では、その代表的事例として独自に研究・計画した「和田吉野川」(熊谷県土整備事務所管轄)の改修計画が紹介されました。
参加者は、国の研究機関・県の行政担当者・地域の市民団体・建設業者など約80名が参加し、都市河川の問題や丘陵地帯の蛇行河川の工事計画や保全方法など、積極的な意見交換がなされ、有意義な研修会となりました。
■研修会場の風景です。⇒ 
■講演者の発表事例。 ⇒
滑川町立月の輪小学校4年生(3クラス・120名)の環境学習を支援しました。雨天のため、市野川蛇行河川の自然観察会を中止し、校内で埼玉県県水環境課や財)河川環境管理財団製作のDVDや環境地図などを利用しながら行いました(主催:市野川水系の会 / 協力;比企の川づくり協議会)。
↓写真:校内での環境学習風景
Ⅰ.自然で健康な川の特徴を学んだ。
①きれいな水がたくさん流れている
②川岸が自然護岸でコンクリートがない
③蛇行や瀬・淵がある
④河畔林や土手がある
⑤きれいな水に棲む魚がいる
⑥きれいな水に棲む水生昆虫がいる
⑦堰やダムがない
⑧工場や家庭の排水が流れ込まない
⑨川で遊んだり泳いだりしたい気分になれる川
Ⅱ.川遊びの「5か条」とは?
1.施工者:東松山農林振興センター、土地改良区
2.現場説明(入間川釘無橋下流 左岸)
消波ブロックは、全体的に地盤沈下を起こしアユ、その他魚類の遡上が不可能なため、左岸側に流路(魚道)を、26年度渇水期(冬季)に竣工した。
渇水期にも拘わらず、コンクリート現場打ちによる流路の地点毎流速はそれぞれ異なっており、最大流速は約1.5m/s程計測されたので、豊水時・平水時に稚アユが遡上可能かどうか、27年度に目視観測していく必要がある。階段状に造成したプール溜り、現場作りの突起状制水工は、流路護岸と流速減衰効果をもたせた工法というものである。
入間川の大臣管理区間で、最大障害物であった菅間堰のアユ遡上障害物は、すぐ上流の寺山堰(棚田式魚道竣工済み)と併せて、取り敢えず解決されたものと思われるので、今春のアユ遡上期が楽しみである。
笹井堰の現場打合せ協議の写真は、以下の添付PDFをクリックして下さい。
⇒菅間堰・笹井堰の魚道見学、打合せ協議.pdf
明けましておめでとうございます。当協議会のホームページをご利用の方々、本年もヨロシク、お願い申し上げます。
早速ではありますが、「埼河連」からの研修会ご案内と若干の現場報告(1/4見学)をさせて頂きます。
■■■埼玉”いい川”づくり研修会の案内■■■
1.日時:1月29日(木)10:00~16:20 受付9:30~
2.会場:朝霞市産業文化センター3階ホール(東武東上線朝霞台駅から徒歩3分)
3.参加費など:資料代として、¥500ー
4.共同主催:埼玉県河川環境団体連絡会(略称「埼河連」)
〃 NPO法人全国水環境交流会
後 援:国土交通省(予定)、埼玉県、埼玉建産連
5.プログラム案→埼玉”いい川”づくり研修会.pdf
上記PDFチラシを参照して下さい。
6.■付帯資料(見学会のPDF写真)と現場説明■
→和田吉野川の現況(H27.1.4).pdf
プログラム案にもあるように、報告3「埼玉での多自然川づくりについて」では、熊谷市と東松山市堺を東流する、和田・吉野川の河川改修を事例として、熊谷県土整備事務所 もしくは埼玉県河川砂防課からの発表報告が予定されています。
そこで、1月4日(日)11時より、「埼河連代表委員」(4名)と比企の川づくり協議会(4名)とで現地視察会を催して、国407号(橋)を境に下流(和田川・吉野川共に)では工事着工中、上流では約1Km区間(蛇行部あり)が今後「多自然川づくり」で設計・施工していくのかどうかを検討中、という現場を視察してきました。
洪水常襲地帯の河川改修ということで、環境面での配慮よりも、喫緊の治水工事が優先された「典型的な定規断面工事」が施工されてきましたが、今後の吉野川蛇行部をどのように”いい川づくり”を計画していくのか、熊谷市の市民団体と共に注目していきたいと考えております。 以上
■日時:平成27年2月8日(日)10:30~16:00(午前・午後の部)
■会場:さいたま市民会館うらわ 全館(JR浦和駅西口徒歩6分)
■主催:埼玉県環境部水環境課 浄化槽・川の国応援団担当(TEL:048-830-3088)
協力:埼玉県河川環境団体連絡協議会(埼河連)
■詳細(分科会情報):詳しくは、次の添付資料【通知】をご覧頂くようお願い致します。
→【通知】川の再生交流会の開催.pdf

滑川町では、10月18日(土)町政施行30周年記念の事業の一環として、羽尾地区の市野川周辺のクリーンアップキャンペーン(清掃活動)を実施しました。
日頃、羽尾地区の蛇行河川の環境美化活動を実施している「市野川水系の会」の皆さん、地元住民など約60名の参加を得て、【高橋→両家橋】と【高橋→羽平橋】の2つのルートに分け、軍手・ゴミ袋を支給された美化活動部隊は、堤防付近や農道に散らばっているゴミ収集と分別にひと汗をかきました。
参加された町民の皆さんは、蛇行河川を真近かに接しながら市野川の自然の豊かさ・貴重さを改めて実感すると共に、今後のプロムナード計画にも積極的に参加して戴ける第一歩を進めたことに、大いに評価していきたいと思います。
写真1.美化活動に集まった皆さん→
写真2.堤防・農道に捨てられたTV→
先にお知らせしましたように、10月4日(土)、武蔵漁業協同組合との共催で「魚影豊かで、県民に親しまれる水辺環境づくり」の一環として、生き物調査を実施しました(小川町in槻川)。
台風18号が近づく気象配置にも拘わらず、好天に恵まれて、地元エコクラブの児童達・保護者約40名の参加を得て、有意義な調査を完了しましたので、埼玉県水産研究所等へお送りしたリポートを以下に添付致します。
→H26年度ふるさとの川増殖事業生き物調査in槻川.pdf
埼玉県の内水面漁場管理委員会では、H19年度より水産業活性化対策事業を継続しており、その一環として持続的養殖生産の「産卵床造成」等を計画してきました(添付資料の2ページ参照)。
具体的には、「地元住民・NPO等と漁業協働組合の共助」によって、産卵床の造成・隠れ場所設置・放流体験・生き物調査を進めることです。
私達が活動する地域では、武蔵漁業協働組合がその任に当たっており、当協議会の運営委員を通じて、共催・共助で魚影豊かで、県民に親しまれる水辺環境づくりを、協働する計画を提案されました。
過去3年間「武州・入間川プロジェクト」等で、「コクチバス撲滅作戦」を担当してきた経緯もあり、近年減少している魚類資源の確保と良好な釣り場の拡張を求めて、漁協からの提案申し込みを受けて、今年度は『槻川生き物調べ(パトリアおがわ裏)』(10月4日)を実施することになりました。
奮って、ご参加をお願い致します。
⇔槻川生き物調査チラシ
槻川生き物調べ(パトリアおがわ 水辺).pdf

「市野川水系の会イン滑川町」の新会長(:日下様)より、年次総会の席上で紹介があった『キツネノカミソリ観賞会』日程などのスケジュール等が決定しましたので、チラシ添付をもってお知らせ致します。
日時:8月10日(日)受付9:00~、自由解散
場所:滑川町羽尾地区(蛇行河川B地区中ノ島)
参加費無料
詳しくは、次のチラシをご覧下さい。
⇔26年度 キツネノカミソリ観賞会.pdf.pdf
[都幾川で川遊び]のご案内
比企の川づくり協議会では、第9回[都幾川で川遊び in ときがわ町]に協力します。
日時:2012年8月2日(土) 9:00〜12:00
集合場所:ときがわ町立玉川小学校プール下の河原
主催:もりんど(ときがわ町)
募集:「子ども見守り」&「魚捕り」のボランティアを募集しています。
詳しくは、下記のチラシ(pdf)をご参照下さい。
⇒'14ときがわ町で川遊び.pdf
1カ月先の当協議会主催の『7.5河川見学会』開催チラシを添付してお知らせ致します。
今回は、2年前のゲリラ豪雨によって羽尾地区蛇行河川のC区間の仮護岸工事が崩壊した結果、土砂流出によりB区間の蛇行河川が埋没したので、東松山県土整備事務所(河川砂防部)から、その復旧工事(土砂浚渫)と新たな護岸工事の進捗状況や今後の工事計画を説明・案内して頂く予定になっております。
併せて、滑川町役場からの「プロムナード構想」の説明や、市民団体「市野川水系の会イン滑川町」の皆さんからの蛇行河川・中ノ島の保全活動や地元要望などをお聞きする計画です。
見学コースについては、水辺散策路が未整備であるため、渡渉しないで河川横断する箇所が少なく、詳細ルートはこれから作成して、開催日当日に配布する計画です。
「いい川づくり」にご関心のある方々や、お知り合い・諸団体への広報がたをお願いする次第です。
⇒見学会案内チラシ 川の日・見学会 7/5(2).pdf
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |