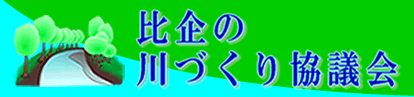 |
 |

11月7日(土)、東松山市と吉見町の境に在る吉見百穴前の市野川高水敷で、第12回目のクリーンアップ作戦(清掃活動)が実施されました。11回目より、東松山ロータリークラブを中心とした13団体の協議会方式で実施されており、私達比企川協もその一翼を担ってきました。
⇒吉見百穴前の河川敷で開会式

700名の参加者で盛り上がった「作戦」の主なイベントは、「市野川両岸の清掃活動」と「川に親しむ(生き物採取・展示)」、「地域間交流(豚汁会)」で構成されており、当協議会からは3個のモンドリ網と1個の定置網での生き物採捕を行い、地元自治会や老人クラブ連合会、小・中学校の児童・生徒達に展示・説明を行いました。
⇒生き物の展示・説明を行う児童スタッフ達




10月4日のホームページで紹介した、比企フェス・川の魅力実感イベントが、10月11日(日)ときがわ町新玉川橋周辺にて開催されました。開催準備時8:00頃には、小雨降る天気状況でしたが、徐々に好天模様となり、10時開会式・表彰式には来場者が増え多くの参加者となりました(午後3時の最終来場者数は、約4500人となった)。 ⇒ 詳細記事:埼玉新聞H27.10.15.pdf
我々の出展ブースは、もりんど(代表:山本悦男さん)を代表として、NPO荒川流域ネットワークの方々と三者共同で設営されました。担当したイベントは、「ときがわの生き物大調査」班と「川の耕し」班で、前者は来場者の親子参加をめざし、後者は川の生き物再生のための実演という趣旨で、実施されました。
水槽に展示された、魚類・エビ・カニ・水棲昆虫は、県立川の博物館の藤田学芸員による同定や説明が行われ、親・子ども達や上田清司県知事・関口定男ときがわ町長等の観察・視察が楽しく行われました。
川の耕しは、水温が低く来場者の参加はなく、協議会々員やNPO荒川ネットワークの方々によるジョレンやツルハシなどで「地道な川作業の実演」で、生き物再生(水生昆虫や魚類の増殖など)を訴える出し物となりました。
10月10日、東松山市の松山市民活動センター、ウォーキングセンター前庭で開催された「環境みらいフェア」に、共同出展しました。
岩殿満喫クラブ(代表:稲田滋夫さん)は、『岩殿丘陵の「農」のめぐみ』(森・里・川の連環チームで、里山再生)、市民の森保全クラブは『森のクラフト体験』(市民の森から里山再生)を出展し、小規模ながら比企の川づくり協議会は簡易測定パック(COD)で九十九川上流の水質測定をしました。
サトイモなど農産物の販売や松ボックリのクラフト体験に、多数のお客さん、参加者があり盛況でした。また、水質汚濁の著しい「施設排水管」には、興味のある方々と情報交換もできました。
ときがわ町のもりんど(代表:山本悦男さん)が参画して、県・町・青年会議所と企画して頂いた『ドキドキ♡わくわく☆ときがわと遊ぼう‼』が、10月11日(日)10時より、ときがわ町新玉川橋上流区間にて実施されます。
詳細は、「比企青年会議所」のHPで見られ、添付資料は、その会議所のHPから掲載させて戴きました。
⇒
また、イベントの内容は次の通りです。
●イベント概要
1 開催日時:平成27年10月11日(日)10:00~15:00
2 開催場所:ときがわ町都幾川(玉川橋~新玉川橋間)
3 主 催:埼玉県 共催:ときがわ町
比企青年会議所35周年記念事業「比企フェス」と合同開催
4 目 的:多くの県民に川遊びを通じて」川の魅力を実感してもらうことにより
「川の国埼玉」への理解を深め、合わせて県の取組をPRする。
5 企画内容:①清流を実感する催し②安らぎを実感する催し③にぎわいを実感する催し
④川の安全を実感する催し⑤集客を図る催し⑥その他
●もりんど担当企画:清流を実感する催しの「ときがわの生き物大調査」と「川の耕し」
1 「ときがわの生き物大調査」班
2 「川の耕し」班
今回の大水害では、比企地方を東流する2つの河川でも、国が流量・水位観測する地点で、早めに氾濫危険水位をオーバーして16時頃には、東松山市の唐子・高坂・野本・下松本の68世帯に避難勧告が出されました。市野川の中流域(吉見百穴付近)に自宅を構える筆者(渡辺)は、即刻マイカーで活動拠点の現状を把握するために、「天神橋流量・水位観測地点」~「滑川との合流地点」~「吉見百穴前(県道27号東松山橋)」~「旧流れ川橋(新宿小学校東)」での水位状況を緊急視察を行って、運営委員&会員に報告しましたので、水位上昇した市野川中流域の河況をご覧頂きたい。
⇒緊急現地視察を報じた水位・流況
氾濫危険水位の市野川 現場視察報告(重陽の日).pdf
⇒9日 氾濫危険水位【20.15m】を約0.2mオーバー
幸いにも、9.9の18時以降は小降りになり水位も低下したので、市野川は20:40に、都幾川は21:40に避難勧告は、解除され甚大な被害や災害報告は無かったものの、平成11年の8月豪雨以来の「緊張感と焦り」を以って、終日過ごしたことをお知らせ致します。
⇒翌10日には、3.50mも下がった水位(標)








8月2日(日)には、二瀬橋左岸(嵐山町)にて親子魚捕り、川遊びが実施されました。
主催は、武蔵漁業協同組合とNPO法人荒川流域ネットワークであり、当協議会員からも6名のスタッフとして地曳網設置や安全見守り等の協力を行ってきました(スタッフ総数20名)。
地曳網は、二瀬橋上・下流に瀬張り網を2箇所設置して、瀬張りより下流から刺し網を、ライフジャケット等で安全対策した「親子さん」によって曳き上げるという漁法で実施されました。
地曳網を引く親子さんとスタッフ⇒
過年度の秋季の実施では、25㎝級の落ちアユが数多く採捕されたが、今夏は数匹のアユに留まった。
漁網の中で数多く採捕された魚種はウグイ(地方名クキ)であり、20㎝級~10㎝級のものが多く100尾前後の漁獲と見受けられました。
刺し網や投網で採捕された、数多くのウグイ⇒
この日も、猛暑の中でのイベントであった為、鴻巣市の三谷釣具店の参加でサービス提供される、恒例のカキ氷は飛ぶように出回り(塩焼きアユは、那珂川水系のもの)、橋の下で涼を取りながら、捕れた魚の説明や外来種の異常繁殖(ミナミヌマエビ)などの現況生き物を学習することが出来ました(講師は、埼玉県環境国際センターの金澤光さん)。
ドジョウの説明と、ミナミヌマエビの生き物現地学習⇒
7月25日(土)、市野川水系の会イン滑川町では、過去2~3年の間に保全活動を行ってきた、市野川羽尾地区(蛇行河川)のキツネノカミソリ群落保護・保全活動を行った。
会員15名は、約3,000㎡の群落地に落ちているゴミや枯れ木などを取り除き、8月に咲き誇る時の群落保全の為に、散策通路境界杭を打って、通路を示すトラロープ張りを実施しました。
高橋付近で杭打ちする会員⇒
高橋から中ノ島に降りる木道も1年を経ると、朽木になっているため、新たな木材と交換し、見学者や子供達が安全に散策できるように整備し直しました。猛暑のため、蛇行B区間のみの作業になりましたが、A区間のキツネノカミソリ群落もあるので、8月8~9日(土・日)の「鑑賞会」までにもう少しの対策を講じるとのことであった。
暑い日に、ご参加頂いた会員の皆様に感謝申し上げます。
作業を終え、全員でパチリ⇒





■日時:2012年8月1日(土) 9:00〜12:00
■集合場所:ときがわ町玉川たまがわ花菖蒲園対岸の河原
■主催:もりんど
詳しくは、次のチラシ(pdf)をご覧下さい。⇒'15-川遊び-もりんど.pdf

参加者は、県内の市民団体からの参加者も多く、主催者・スタッフを含め、総勢で39名の参加者がありました。現地での午前の部・見学会を終えた後、地元平塚新田自治会集会所にて昼食を取り、午後の部・話題提供と地元からの活動事例発表が行われた。
⇒現地見学を終えて集合写真
【市民による意見交換会(話題提供と活動事例発表)】
1.「和田吉野川における多自然川づくりの改修事業計画の概要」
埼河連 小林 一巳さん
*資料は、熊谷県土整備事務所作成のものを使用した。
2.「和田吉野川の今昔」 平塚新田自治会会長 奥田信夫さん
3.「和田吉野川に生息する生物」 平塚新田自治会 大久保茂夫さん
4.「ほたるの一生」 熊谷市ほたるを保護する会
岡部 幸夫さん
⇒自治会集会所にて、市民交流・意見交換会



埼玉県がH24年度より、ときがわ町・東松山市・嵐山町・小川町の都幾川水系で「川のまるごと再生」を実施しており、それぞれの地区で自治体・住民で組織する検討部会から提案された里川づくりが行われ、今年度が最終年となり県が実施中の整備状況や、今後、自治体が実施予定の整備計画などが現地説明等で紹介される予定です。
当協議会の恒例イベントとして、『川の日・7月7日』に近い7月4日(土)に第15回河川見学会を挙行する運びとなりました(添付チラシ表・裏2ページを参照)。→チラシ 川の日・見学会 7/4(最終版.pdf
つきましては、当日参加者受付や資料配布など、開催時間より30分早めの8時30分に集合場所(ときがわ町役場本町前)へ来て、スタッフ支援して頂ける方を募集いたします。 連絡先:渡辺 仁まで(090-5573-1028)
川魚の冬季の隠れ場で棲家になる「石倉」(下の写真)の設置は、平成26年度水産庁予算である水産多面的機能発揮対策事業の助成を受け実施されたものです。この事業は武蔵漁業協同組合と地域住民等が協力して、釣教室や河川清掃等を行ない豊かな川づくりを目指したものです。

「石倉」は1m四方 深さ50cmの樹脂ネットに100~150個程度の大きな石を詰め沈めたもので、魚類の保護・増殖を目的としています。特に冬期間は多くの魚類が石の隙間で越冬し、水ぬるむ春を待つ「棲家」となります。白石漁協監視員達が調査したところ、一つの倉には2000~4000尾の魚類が越冬していたそうです。ウナギが生息することを期待して、それぞれの倉に1mほどの塩ビ管を埋め込みましたが(下写真)、この間一匹も確認されなかったとのことです。
参加した協議会会員(7名)は、持ち寄った鉄製レーキや熊手などで、土砂やシルトで埋まっている転石や底石をひっくり返し「浮石=隙間をつくる」状態に戻す河床たがやしを行った。既にトビゲラやヒラタドロムシ、カゲロウなど多く付着していたが、これらの水生昆虫が干上がらない程度に水深を確保しながら耕し(ひっくり返し)作業をおこなった。
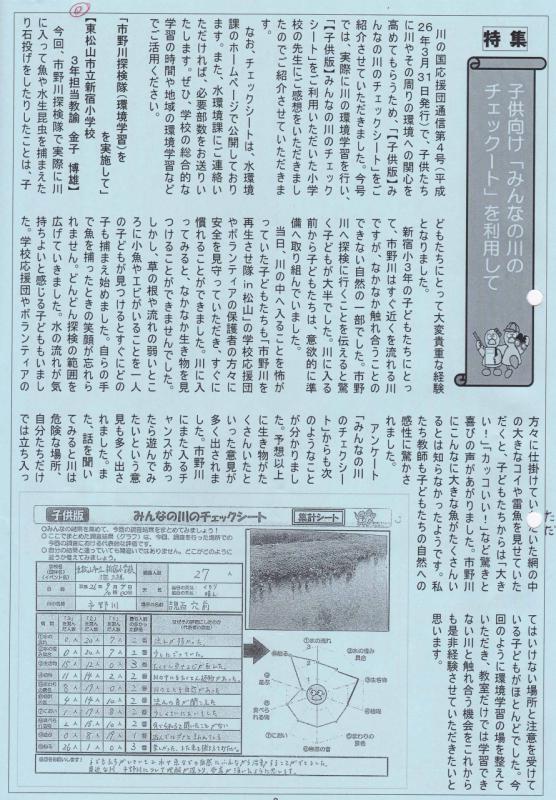
3月21日(春分の日)、熊谷市南部を東流する和田吉野川の多自然川づくりへ向けて、埼河連・熊環連の呼びかけで平塚自治会・ホタルを保護する会・エコネット熊谷・中央漁協・比企の川づくり協議会の市民・住民団体のメンバー約20名が、熊谷市平塚自治会館に集まり全体の連携強化を計りながら、熊谷県土整備事務所への要望・協働していくための第1回目の会合を開催した。
当地の河川改修の第一眼目は洪水常襲地帯での「治水」にあるが、国道407号より上流は「橋の架け替え以外は、現状の河川形態を維持する」「コンクリート工法は最小にして、石積み・土羽を基調にする」ことを強く要望していくことが確認されました。
当地の用水路では、ゲンジボタルが生息するので、わざわざ都心からカワニナを盗みにきている者達も多く、これらの保全につながる河川改修や、右岸側の2~300mの長さの河畔林(クヌギ・コナラなど)の保全・管理を期待したいなど、多くの住民希望が述べられた。漁協組合員の方からは、オイカワやコイなどの繁殖が維持されることを期待したい(ウグイは、見られないとのこと)などの意見も述べられた。
埼河連の大石・小林・山本代表理事の方々からは、今後4月末までに第一回目の要望書を取りまとめ、概略設計を発注・設計を担当する熊谷県土整備事務所へ提出し、問題提起、協議等を行うこと。9月末までには、設計修正も含くむ第二回目の要望書の取りまとめを行うこと、などの概略活動スケジュールが確認されました。
写真;熊谷市「平塚自治会館」で、市民・環境団体の協議風景
↓
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |